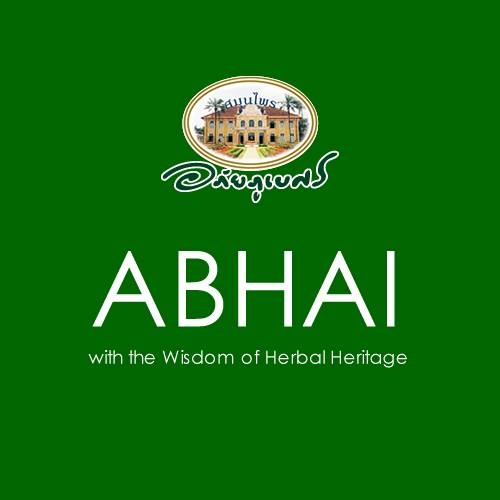足元を美しく生まれ変わらせる、アバイブーベの自信作「フット&ヒールケア」。天然ハーブの成分を贅沢に使い、研究者が「理想のクリーム」と称賛するクリームは、足元のケアだけに使うのはもったいないなぁ、顔や手に使えるのがあるといいのにと思いませんか?
でも、ハンドクリームにフットクリーム、アクネクリームに敏感肌用クリームなど、用途に応じて様々なコスメを準備するのも大変ですよね。そんな時こそ、「フット&ヒールケア」の出番!
名前がピンポイントのため、足元専用と思われがちですが、ハイブランドのコスメに配合されている高品質な天然ハーブが贅沢に使われているため、顔を含む全身に安心して使うことができるのです。
そこで今回は、アバイブーベのスタッフが実践している「フット&ヒールケア」の色々な使い方をご紹介します。